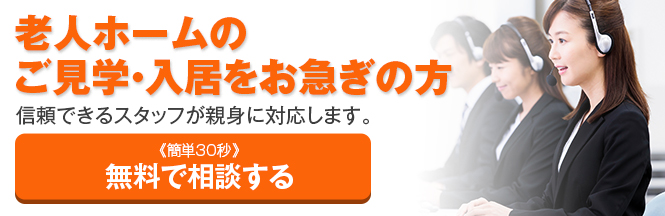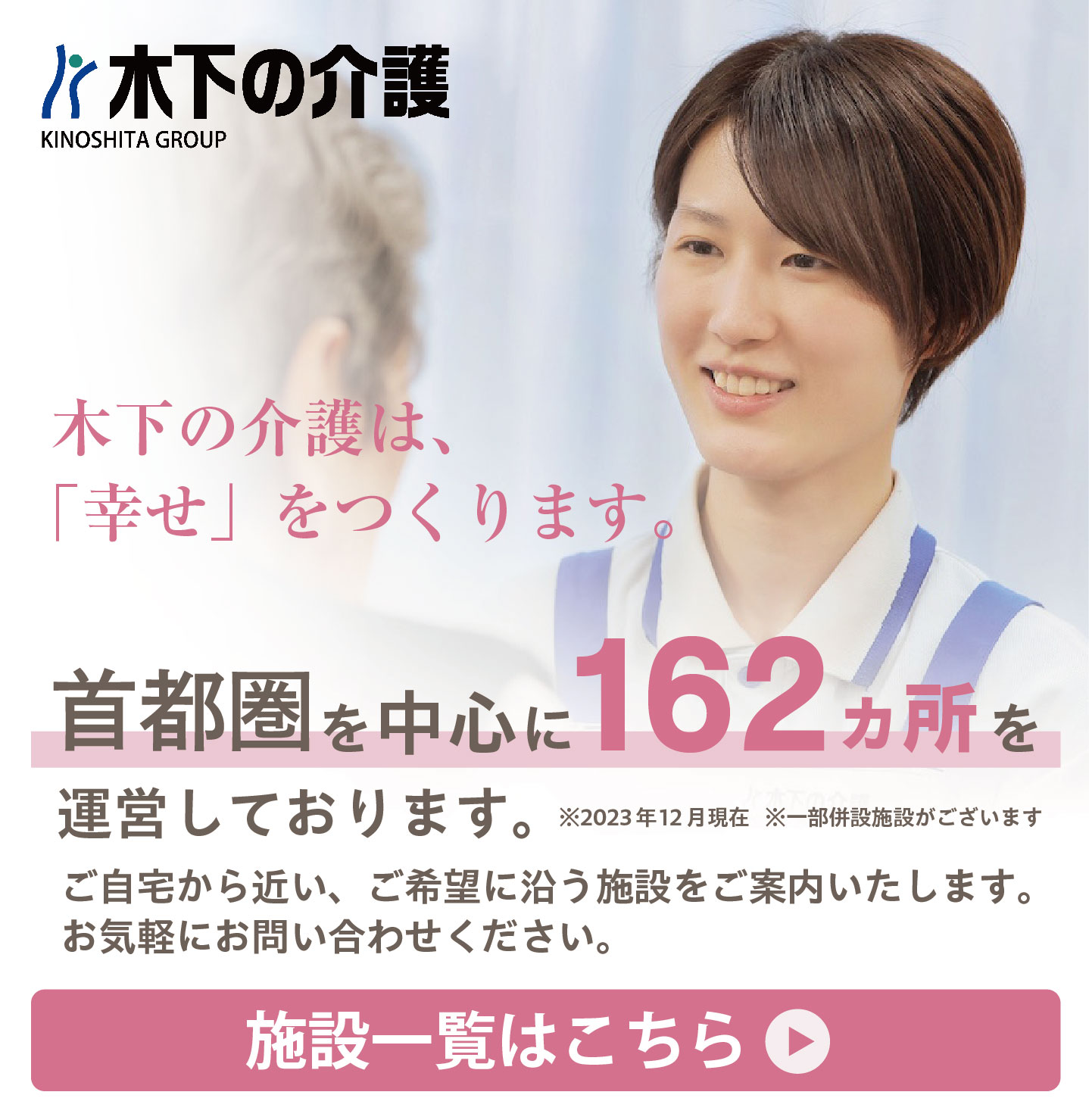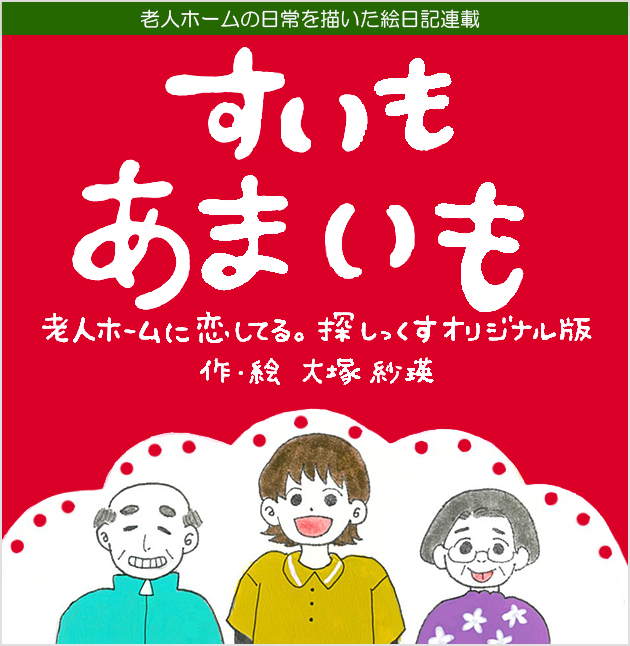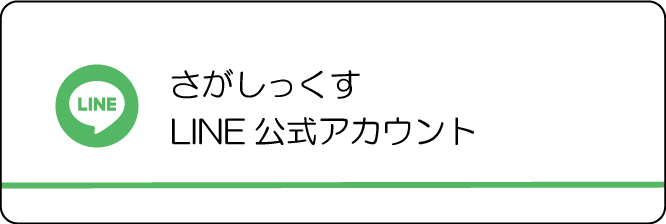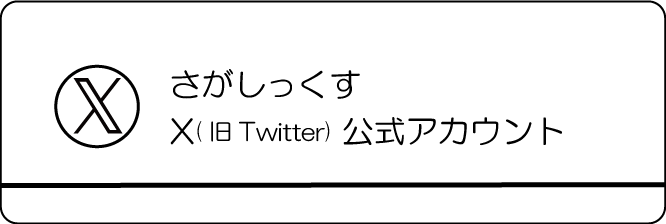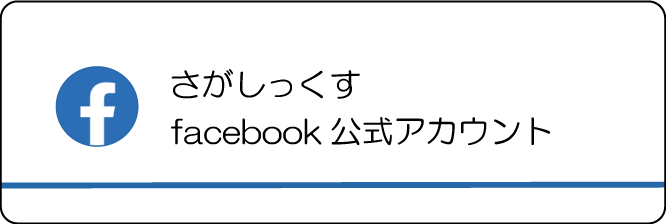日常的な生活支援や身体介護を要する高齢者は、要支援1・2または要介護1~5の7段階に分類されることはすでにご存じの方も多いでしょう。一方で、「要介護度の判定基準までは詳しくわからない...」という方もいるのではないでしょうか。今回は、要介護認定の大きな判定基準となっている、障害高齢者と認知症高齢者の「日常生活自立度」について解説します。
日常生活自立度とは?
「日常生活自立度」とは、認知症や障害のある高齢者が独力で日々の生活を送れる程度をレベル分けする際の基準値です。認知症高齢者は9段階、障害のある高齢者は4段階に分類されています。
この日常生活自立度を最初に判定するのは、介護保険の申請時です。自治体の窓口で手続きを終えると、担当者(調査員)が自宅を訪問します。高齢者と面談を行い、その調査内容をもとに調査員がレベル分けをします。
その後、コンピューターによる一次判定、主治医が作成する「主治医意見書」の内容をふまえた二次判定を経て、最終的な要介護度(または要支援度)が決められるのです。
障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)の4段階

この判定基準は、障害のある高齢者の日常生活自立度を客観的かつ短時間で判定するために作成されたもので、「寝たきり度」と呼ばれることもあります。
ランクJ(生活自立)
病気やケガの後遺症によって何らかの障害はあるものの、日常生活ではほぼ自立しており、独力でも外出できる状態です。
電車やバスなどの公共交通機関を使い、比較的遠方まで外出可能な状態をJ‐1、自宅から徒歩圏内で移動できる状態をJ‐2と分類しています。
ランクA(準寝たきり)
屋内での生活はほぼ自立しているものの、外出については付き添い(介助者)を必要とする状態です。「準寝たきり」「寝たきり予備軍」と呼ばれることもあります。
睡眠、休息時以外はベッド外で過ごし、介助者とともに外出する機会の多い状態をA‐1、外出の機会が少なく、寝たり起きたりを繰り返している状態をA‐2と分類しています。
ランクB(寝たきり)
屋内での生活にも何らかの介助が必要で、座位を保ちながらも日中はベッドの上での生活が主体となる状態です。
独力で車いすへの移乗が可能で、食事や排せつもベッド外で行える状態をB‐1、車いすへの移乗から、食事、排せつなどすべてにおいて介助者が必要な状態をB‐2と分類しています。
ランクC(寝たきり)
ランクBよりも障害が重く、1日中ベッドの上で過ごし、すべてにおいて介助を要する状態です。
寝たきりながら独力で寝返りが打てる状態をC-1、寝返りできない状態をC‐2と分類しています。
認知症高齢者の日常生活自立度の9段階

次に、認知症高齢者に対する日常生活自立度の9段階(Ⅰ、Ⅱ、Ⅱa、Ⅱb、Ⅲ、Ⅲa、Ⅲb、Ⅳ、M)について見てみましょう。基本的に数字が大きくなるほど自立度が低くなり、手厚い日常支援や介護が必要となる傾向にあります。
Ⅰ)何らかの認知症を有するが、日常生活は家庭内および社会的にほぼ自立している状態
在宅生活が基本で、家族や支援者がいれば、ほぼ困ることなく日常を送れます。
Ⅱ)日常生活に支障をきたすような症状・行動や意思疎通の困難さが見られるが、誰かが注意していれば自立できる状態
在宅生活を基本に、独力での生活が困難な場合は日中の居宅サービスを利用して支援を受ければ一人暮らしを継続できるレベルです。
Ⅱa)日常生活に支障をきたすような症状・行動や意思疎通の困難さが家庭外で見られるが、誰かが注意していれば自立できる状態
こちらも在宅生活が基本です。ただし、環境が目まぐるしく変わる屋外は、認知症の高齢者にとって状況把握だけでも大変な場所です。道に迷ったり買い物での計算ができなかったりといった症状が見られる場合はこのレベルに該当します。
Ⅱb)日常生活に支障をきたすような症状・行動や意思疎通の困難さが家庭内で見られても、誰かが注意していれば自立できる状態
慣れ親しんだ自宅でも認知症の症状が出る場合には、Ⅱaよりも重度と判断される傾向にあります。具体的には、服薬管理や留守番(電話応対、来客応対)ができないような状態を指します。
Ⅲ)日常生活に支障をきたすような症状・行動や意思疎通の困難さが見られ、介護を必要とする状態
Ⅱよりも認知機能が低下しており(着替え・食事・排便・排尿がうまくできないもしくは時間がかかるなど)、見守りや支援を必要とする在宅介護の認知症高齢者がこのレベルに当てはまります。
ただし、一時も目を離せない状態とは言えません。家庭の事情によっては居住系サービスの利用を検討することも可能です。
Ⅲa)日常生活に支障をきたすような症状・行動や意思疎通の困難さが日中を中心に見られ、介護を必要とする状態
Ⅲの症状が日中に見られる状態です。認知症高齢者が一人暮らしの場合や、家庭の事情で頻繁な見守りや支援が困難な場合は、居住系サービスの利用を検討すると良いでしょう。
Ⅲb)日常生活に支障をきたすような症状・行動や意思疎通の困難さが夜間を中心に見られ、介護を必要とする状態
認知症の程度としてはⅢaと同等ですが、徘徊や大声を出すといった症状が夜間でも見られる場合はこのレベルに該当します。生活の昼夜逆転によって、本人の健康状態が悪化する可能性が高く、Ⅲaより認知機能が低下しているとみなされます。
介護にあたる家族の労力も大きくなるため、居住系サービスを夜間対応のものとあわせて利用することも検討しましょう。
Ⅳ)日常生活に支障をきたすような症状・行動や意思疎通の困難さが頻繁に見られ、常に介護を必要とする状態
Ⅲと比較して、認知症の症状が高い頻度で現れる状態です。在宅介護が難しくなり、老人福祉施設や居住系サービスの利用を検討せざるを得ないレベルだと言えます。
M)著しい精神症状や問題行動あるいは重篤な身体疾患が見られ、専門医療を必要とする状態
せん妄や幻覚が見られるケースや、暴力行為、自損行為(故意に自分自身に傷害を加える行為)などが見られる状態です。こうした精神疾患が原因で起こると見られる症状は、専門医の管理下での治療が必要です。こちらのレベルに限り、認知症の程度に関係なく適用されます。
判定の際は、まずⅢの状態(ADL低下の有無)を確認して、問題がなければⅡの状態(IADL低下の有無)を確認します。
日常生活自立度の判定における問題点

前述の通り、日常生活自立度は要介護度を決定するうえで重要な基準です。一方、解消すべき問題点もあります。
まず、日常生活自立度は調査(聞き取り)内容によって判定されるため、調査員の認知症への理解度、経験によってその結果にバラツキが出ます。また、突然家に来た見慣れない人に自分のことを根掘り葉掘り聞かれれば、不信感を抱いたり緊張してうまく言葉にできなかったりする高齢者も少なからずいるでしょう。
また、普段は受け答えや日常生活動作に問題がある方でも、知らない人の前ではしっかりした受け答えや動作ができてしまうこともあります。誰もが普段通りのリラックスした状態で面談に応じられるわけではないため、当日の面談結果だけで重度の判定、ないしは軽い判定が下されてしまう可能性もあります。
なかには同居する家族が質問されるケースがありますが、長年別居したあとに一緒に暮らし始めた人や、そもそも親子間のコミュニケーションがあまり円滑でなく、親に対して家族が正しく理解できていない人もいるでしょう。
こういった場合に、調査員に正確な情報が伝わらず、正確な判定に不利な影響を与えることも考えられます。
家族も判定基準を理解して面談のサポートを

介護保険サービスを受けるなら、自治体から派遣される調査員との面談は欠かせません。
一方で、自分が認知症や要介護状態、または予備軍であることを認めたくない高齢者も多く、見栄を張ってしまうケースもあるようです。
家族は要介護認定の判定基準や日常生活自立度の段階を理解し、面談時に本人のサポートを行うと良いでしょう。
▶全国の認知症ケア充実の施設特集はこちら
▶全国の有料老人ホームを探す